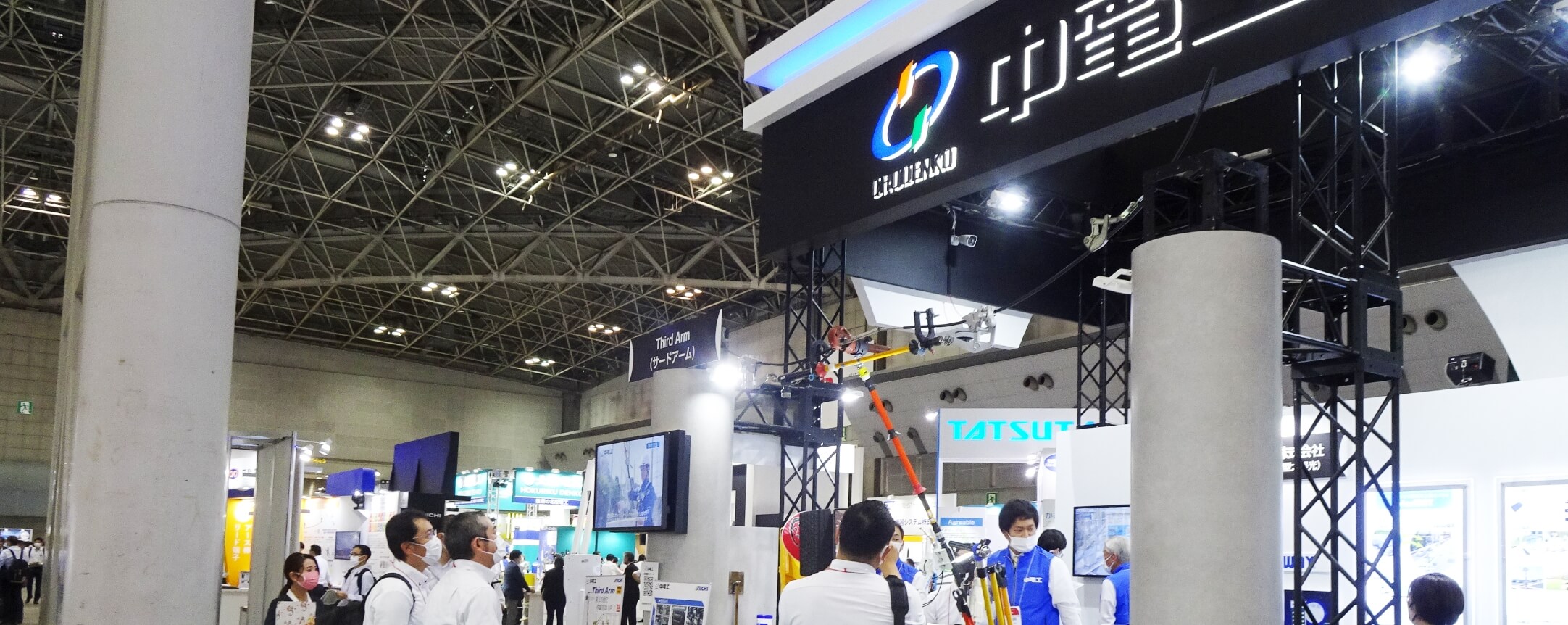WORK
PROJECT
STORY
03
ZEB(Net Zero Energy Building)推進プロジェクト
Net Zero Energy Building(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)、通称「ZEB(ゼブ)」は、快適な室内環境を維持しながら、負荷抑制、自然エネルギー利用、設備システムの高効率化によって、一次エネルギーの収支ゼロを目指した建物のことをいう。日本政府が2019年に掲げたSDGsアクションプランにおいても、建築物の省エネ化、低炭素化の推進が挙げられている。こうした社会情勢の中、中電工では岡山統括支社の新社屋建設に関して、ZEB認証を目指して取り組もうという案が持ち上がる。
何もかもが初めてのZEBへの取り組みはどのように進んでいったのか。そして、その後の事業発展についてもプロジェクトの中心を担ったFに話を聞いた。
PROJECT MEMBER
※社員の所属は取材当時のものになります。
-
F.S
ソリューション営業部 エコソリューション担当
新社屋建設のZEBプロジェクトの発案者であり、現在もさまざまなリニューアル案件を手がけるZEBのスペシャリスト。施工管理、設計、営業とさまざまな経験と知見を持つ。
Chapter 01


中電工がZEBに向けてスタートを切ったのは2017年だ。政府が省エネに向けたさまざまな施策を推進する中、2017年4月以降、延べ面積2,000m²以上の新築非住宅建築物などは省エネルギー基準の適合が義務化されるようになり、その基準より一歩先へ進んだZEBが、環境建築の選択肢の一つとして注目されるようになった。一方、中電工では岡山統括支社新社屋の新築計画が浮上し、新社屋に導入する技術案を社内で出し合っていた。
Fのいるソリューション営業部は、太陽光発電を採り入れた建築物を扱うプロジェクトを機に立ち上がった組織で、エネルギーソリューションを専門とする部隊だ。新社屋計画案に参加していたFはこれを絶好の機会と捉え、迷うことなく新社屋のZEB化を提案した。
「新社屋には何か目玉となるような、新しい技術を取り入れたいと考えていました。中電工が環境関連工事を展開していく上でも、ぜひZEBに挑戦したいと思いましたね。周りも同じ思いだったようで、提案自体はスムーズに通りました」
新社屋をZEB導入を前提でリニューアルする決定と同時に、経済産業省が展開するZEB実証事業(補助金)へのエントリーも決まった。これは、条件を満たした建築物に対して設計費や設備費、工事費の3分の2が補助金として支払われる事業だ。かくして、中電工初のZEBに向けて新たな挑戦が始まった。
Chapter 02


自社案件だけでなく、顧客に対してのZEB提案などもすべてが手探りの状態で業務は進んでいった。「新しい取り組みに対する期待と不安が入り交じっていました」と、Fは当時を振り返る。
プロジェクトは、岡山統括支社のプランニングを統括する岡山統括支社所属の担当者と、社外パートナーのZEBプランナー※と協力し、一つひとつ進められていった。Fは主にZEB認証に必要な書類作成・申請業務を担当したが、複雑かつ膨大な量の申請書類は、最終的に10センチ厚のファイル7冊分にもなったという。
「初めてのことばかりで苦労しましたが、総合エンジニアリング企業として高い技術力で対応していかなければ、という強い意識を持って進めた結果、無事新社屋のZEB化に成功し、補助金の交付も受けることができました」
またこのプロジェクトの成功を機に、2019年に中電工はZEBプランナー※を取得。お客さまに対する ZEB提案の推進も開始した。設備に関する設計や工事はもちろんだが、ZEB化のプランニングや補助金申請など、ワンストップソリューションで提供できるのが中電工の強みとなっている。
※ZEBの実現に向けて建築設計、コンサルティングなどの面からサポートする専門家
Chapter 03


現在、病院や公的施設、テナントビルなど、中電工が手がけたZEB建築物実績は合計23件に上る。省エネや室内環境の良化、企業のイメージアップ、建物価値の向上などが見込まれるZEBは、今後も広がりを見せていくだろう。ほぼすべての案件に携わるFはZEBの難しさについて、
「ZEB化は、断熱材や高性能ガラスなどで外皮性能の向上を図り、自然換気や昼光利用などを取り入れるパッシブ技術によってエネルギーの需要を減らしつつ、高効率な空調や照明、給湯などのアクティブ技術によってエネルギーを無駄なく使用し、さらにそのエネルギーを太陽光発電などの創エネ技術によって賄うといったステップでプランニングしていきます。ZEB化の可否を判断するためには、『エネルギー消費性能計算プログラム(WEBPRO)』というシステムに建物の必要情報を入力し、基準値内に収まっているか確認する作業が発生します。最初の設計時には問題なかった数値が、工事中の仕様変更で工事完了後に基準から逸脱してしまってはZEB認証されなくなってしまうので、仕様変更の対応については非常に気を使います。遠隔地の工事であっても、フェーズごとにメンバーと直接会って話す機会を設け、できるだけ細かな説明を行うよう心がけています」と話す。
またプランニングだけでなく、補助金申請手続きを代行する場合には、書類作成や補助執行団体との連絡・調整業務が加わる。スケジュールの調整など、協力会社との密な連携が必要となるため、工事前にはZEBのルールや補助事業の要点を共有する説明会を実施し、改めてルール順守や工期管理の重要性を伝えているという。
Chapter 04


ZEBは高効率な設備を初期投資するため、通常工事よりイニシャルコストはアップする。しかし光熱費の削減や補助金の活用など、長期的に見れば顧客にとって大きなメリットを生み、かつ地球環境にも貢献することができる。
「ZEB案件を手がけて良かったと思うのは、どれだけ大変でもその価値があると感じられることです。ZEBプランナーとして初めて担当させていただいたお客さまから『本当にZEB化して良かった』とお言葉をいただいたときは、すべての苦労が報われました。そのお客さまは古くなった建物を新たに建て替えてZEB化されたのですが、ZEB化したことで建て替え前に比べ光熱費が約半分になったそうで、お会いするたびに感謝を伝えてくださいますね」と、FはZEBプロジェクトに確かな手応えを感じている。
脱炭素やSDGsが注目される今日、中電工ではZEB以外の省エネ関連のリニューアル提案も増え続けている。政府や自治体からもさまざまな補助事業が展開されており、お客さまのニーズに合った補助事業を提案し手続きを代行する機会も多い。「まずは中電工が掲げたZEBの年間目標に向けて走り続けること。そして、ZEBに代わる新たな取り組みにチャレンジする機会を常に探していきたいと思います」と今後の目標を語るF。ZEBや再生可能エネルギーなど、環境に配慮した提案を通じ、中電工は今後も第一線を走り続けるだろう。